|
第三回 |
 |
●我々を取り巻く食の世界は。
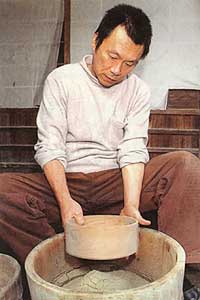 我々を取り巻く食の世界は貪欲にもその食を大量に消費し、大量の残飯が破棄され、おかげで大都市のビル街の朝は烏が逞しく占拠し、住宅街にはタヌキさえ歩き回る。それを動物との共生だと、「かわいい?」と放し飼いのペットのごとく喜ぶ人もいるが、もとをただせば我々人間の貪欲な食い気の不始末に因る。テレビのゴールデンタイムともなれば、少なくとも2局ぐらいは同じ時間に同じような美味しいもの番組をながし、グルメ欲をあおる。「本当に美味しいのか?」わかる由もないバラエティー番組は、同じような顔ぶれが、ふだん着感覚を売り物に、同じような笑いを押し付け、同じようなものを美味しそうに食らい、同じような笑みを満面に浮かべる。タレント気取りの料理人、料理人気取りのタレント。この手のバラエティ番組のスタジオセットは、たいてい赤色にけばけばしく粉飾されていて、我々の欲気をただでも刺激する。
まるで闘牛場の牛が赤い布に猛進するように、カチャカチャ忙しく切り替えながらゴールデンタイムのチャンネルを渡り歩く。昨日あったはずのイタリア料理店、今日行ったらゲーセンに変わっていた。「あそこのラーメンやうまい」と教わって、行ってみたら長蛇の列、後ろに立たっている待ち人の視線を気にしながらあたふたと箸おいて「お勘定!」。
やっぱりそれでもおいしかったと満足して帰る。懲りずにその後3回ぐらい通う。でも3回目には飽きてしまって、「何が美味しいね?ん」。わからなくなってしまう。そう、テレビのチャンネルと同じ、飽きたら渡り歩かなければならないのがグルメの定めである。そこで強い味方がグルメ案内本と婦人雑誌。 赤い色が目につくページめくるとそこは大抵グルメの紹介。また同じことの繰り返し。「どっちみち時間待ちの暇つぶしやから」編集者も読者も同じ発想、同じ共謀者、たいした情報もない、期待もしてない。「本当に美味しいものってなんや?」「僕ら現代人はそれを忘れてしまっている!」「それなら昔はあったのか?」 ちょっと考えてみる・・・。
我々を取り巻く食の世界は貪欲にもその食を大量に消費し、大量の残飯が破棄され、おかげで大都市のビル街の朝は烏が逞しく占拠し、住宅街にはタヌキさえ歩き回る。それを動物との共生だと、「かわいい?」と放し飼いのペットのごとく喜ぶ人もいるが、もとをただせば我々人間の貪欲な食い気の不始末に因る。テレビのゴールデンタイムともなれば、少なくとも2局ぐらいは同じ時間に同じような美味しいもの番組をながし、グルメ欲をあおる。「本当に美味しいのか?」わかる由もないバラエティー番組は、同じような顔ぶれが、ふだん着感覚を売り物に、同じような笑いを押し付け、同じようなものを美味しそうに食らい、同じような笑みを満面に浮かべる。タレント気取りの料理人、料理人気取りのタレント。この手のバラエティ番組のスタジオセットは、たいてい赤色にけばけばしく粉飾されていて、我々の欲気をただでも刺激する。
まるで闘牛場の牛が赤い布に猛進するように、カチャカチャ忙しく切り替えながらゴールデンタイムのチャンネルを渡り歩く。昨日あったはずのイタリア料理店、今日行ったらゲーセンに変わっていた。「あそこのラーメンやうまい」と教わって、行ってみたら長蛇の列、後ろに立たっている待ち人の視線を気にしながらあたふたと箸おいて「お勘定!」。
やっぱりそれでもおいしかったと満足して帰る。懲りずにその後3回ぐらい通う。でも3回目には飽きてしまって、「何が美味しいね?ん」。わからなくなってしまう。そう、テレビのチャンネルと同じ、飽きたら渡り歩かなければならないのがグルメの定めである。そこで強い味方がグルメ案内本と婦人雑誌。 赤い色が目につくページめくるとそこは大抵グルメの紹介。また同じことの繰り返し。「どっちみち時間待ちの暇つぶしやから」編集者も読者も同じ発想、同じ共謀者、たいした情報もない、期待もしてない。「本当に美味しいものってなんや?」「僕ら現代人はそれを忘れてしまっている!」「それなら昔はあったのか?」 ちょっと考えてみる・・・。
そう・・・。心の奥のとっておきの一つはなんと言っても椿の花。僕の父は椿の花が好きで、家には5?6本の椿の銘木があった。 曙という薄桃色の椿。初嵐と言う名の白い椿。2月の冬の空にポンポンと、赤や白や薄ピンクの花が一時に咲く。椿の花はふっくら膨らんだ蕾が愛らしい。精一杯満開に開けば、数日でその重さに耐え切れなくなったのか、ぽとりと地に落ちる。地に散乱した椿の花は、一ひら一ひら風に散らす花よりもなお一層哀れにみえる。僕は満開の椿の大輪を摘んで、花びらが折り重なってすぼんだ軸の小さな穴のからスッーとその蜜をすうのが好き。
花びらのストローを通って、微かに甘くてわずかに花粉の粉の味がする。 花弁だけスポット枝からぬいて、枝先には小さな雌蕊だけがぽつんと寒風にさらされて残っている。隣のお家に大きな真っ紅な薮椿の老木があって、なんと言ってもこの紅い椿の蜜が一番美味しかった。妹と二人、二階の窓から屋根つたいに、そうろとお隣の屋根に乗り移り、真紅の椿の花をそっと口に含んだ。屋根の上の日溜まりに身を寄せて妹と二人で椿をすう。寒さの向こうの方から微かに微かに甘さが僕の舌先にとどいた。僕のたぶん小学校1年生頃の事。
「本当に美味しいもの」その極め付けはやっぱり母の作ってくれたロールキャベツ!父が捏ねた鍋一杯のお好み焼き!僕の家では「お揚げの日」と言うのがあって、油揚の焼いたのに大根おろしいっぱい付けて醤油掛けて食べる。つまりは倹約の日。
そんな後でのロールキャベツの日は美味しかった。でも、「それって今から思えばただの懐かしの癒し系やろ。」「同じもの今食べて美味しいって思えるの?」「ううーん、そうかもしれん。・・・でもやっぱり今で焼いた油揚は好き」「まっかに熟して割れそうなトマトも美味しかった。氷の冷蔵庫で冷たくして頬張った。賀茂のおばさんがだいはち車で売りに来る賀茂茄子、濃い紫色で蔕のところめくると薄紫色してきれい、手で擦るとキュッツキュッツって軽い音がした。油で炒めて生姜醤油掛けて食べた。」振り返れば懐かしの癒しかも知れないけれど、それが僕のまぎれもない美味しいもんの味覚の原点。なんでも手に入る現代っ子の味覚の原点はなんだろう。マクドのハンバーガー、フライドポテト、きんぴらごぼうもローソン仕立て?それともグルメのお母さんが連れてってくれたフランス料理?
父と一緒に鍋一杯のキャベツと特別奮発のひき肉一杯いれて、メリケン粉と卵いれて力一杯捏ねた。自家製お好み焼き。「お前、もう一個卵入れようや。持ってきなさい。」父の顔も僕も楽しかった。母の顔も、妹の顔も笑っていて、もっとも叱られて泣きながら食べたロールキャベツもあったが。賀茂のおばさんの日焼けした顔も元気そうやった。そのおばさんが持ってきた加茂茄子やから、その茄子育てた、まだ会った事のないおじさんの顔もわかるように思える。顔から顔へとローカルな輪が広がる。食文化はもっとも身近なローカルな広がり。グローバルスタンダード一辺倒の現代社会、そこから人の顔が見事に消えてしまって、僕らは大切にしてきたローカルな生活圏を失った。料理はやはり人の顔の見える料理が一番美味しい。僕ら家族が行く数少ない京都のお店、イタリア料理はイタリアらしく変に気取らないいところが好き。僕らはいつも閉店時間超過の居残り客。
御主人は時折イタリアに行かれる。またメニューがふえると期待する。 最近ムースで髪の毛をとげとげにされている。 ぼくも息子の残りのムースをつけてみる。奥さんの笑顔が素敵で話しするのを楽しみにしている。中国東北県出身の家族の中国料理のお店。ここはお母さんがコック長。 全く飾りっけなしのおっかさんの味。「これトマトと卵を出汁で炒めただけじゃないの?」でも美味しい。店の中にはテーブルが6っつしかない。その一つを占領してお父さんが餃子を包む。いつもこの水餃子をたらふく食べるのが楽しみ。日本流お愛想の全くない、働き者の気の強そうな娘さんが店内をひとり切り盛りしている。いつぞや、ちょっと夕方早めに行ったら、店の蛍光灯が全部消えていた。「やってますか?」「どーぞ」中に入ってテーブルに つこうとしたら「ちょっとすいません」娘さんが元気よくテーブルの上に乗って僕らの机の上の蛍光灯一つだけをひねって点した。それが僕はとても気に入っている。京料理の割烹、なかなか行けないが、年に一度ぐらいはいきたい。 ここへは僕らはいつも決まったある友人夫妻といくことにしている。御主人の職人気質の料理はほんまもん。短くなった包丁が美しい。 使い切って細くなって折れそうな白木の鍋蓋の取手までもが美しい。なんでもないふとした素材が、けれど絶妙の間合いで出てくる料理、僕は陶芸をしているが時々その料理の間合いに驚く。「その心おなじやな?」と思う。それから嵐山の吉兆さん。この食に付いての一文の依頼主。若主人邦夫さんは、料理に付いて、食文化に付いて、茶の湯や日本文化に付いて真面目に真摯に悩んだり憤ったり考え込んだりする。考えるだけでなく行動にもおこす。しっかりと自分の顔付けて歩いている。お爺ちゃんが湯木貞一さん、吉兆の創始者。邦夫さんはその3代目。お爺ちゃんがあんまりにも偉大だったから、望まずとも日本料理=吉兆料理みたいなスタイルが世間でできてしまったから、つまり吉兆料理は伝統になってしまったから邦夫さんは大変。でも邦夫さんなら立派な3代目になれると思う。自分なりの吉兆料理のポリシーを お客さんとともに、そしてお店の人とともに作り上げようとしている。 お爺ちゃんも戦後、小さなカウンターの割烹から始められた。茶の湯の世界では偉大な数寄者。
割烹のお店の時からいつも茶の湯釜に湯をたぎらせ客に茶をふるまったと聞く。茶の湯はまさに一客一亭が神髄。文化功労賞までもらわれたけれど、さいごまで顔の見える方だった。
それぞれの顔が見える。その顔が結びつく、個人と個人の出合いと広がり、そのネットワークが食文化の豊かさを養う。何でもお金さえ出せば手に入る時代、人の顔が見えない。そんな時代の焦慮からか、普段着のタレントが過剰な嘘臭い普段着姿を演じる。素人まで出てきてばかな事でも恥ずかしい事でもおくびもなく喋りまくる。普段着顔ならば何でもよい。「大人の嘘よりましでしょう。」そんな事が言い訳になり価値にもなる。本音でもの言う政治家という虚像、エプロン感覚の大臣という庶民の期待。マスコミの論説委員もファーストネームで大臣の名を呼ぶ。バカ臭くて腹立たしくてそして気持ち悪かった。顔が見えない時代、顔見せてますよという虚像がほんまもん顔してまかり通る。どこかで何かが作り上げられ操作されている。その裏側の影に隠れて顔の見えない事をいい事に、BSE狂牛病対応の いい加減さ、それをよいことに嘘の申告をする会社、中国健康食品や残留農薬輸入野菜、しかも残留殺虫剤クロルピリホスの日本の基準値はほうれんそうは0.01ppm,でも大根は300倍の3ppm、これどうなってるのか、さまざまさまざま、いつまでたっても嘘といんちきと金儲け主義と責任のたらい回しは後をたたない。
僕は昔2年程イタリアのローマに住んだ。イタリアの食材は美味しかった。魚を売るマーケットは水曜日にだけ市がたつ。鰯なんかスコップですくって袋に入れてくれる。おかげで半分頭ちぎれた鰯もあるが、それはそれは新鮮で安い。イタリアのビステッカは日本人には「草鞋みたいでかたくてまずい」と不評だが、日本の高級和牛はやたら値段が高くて油ばっかり。子供達は気持ち悪くなるからってこの霜降り高級ステーキは食べない。イタリアの赤身の肉は噛むとジュウシーでお肉の味がする。日本のギトギトの霜降り高級牛はやっぱりどこかおかしい。甘いばっかりの日本のみかん、香りがない。青いうちに刈とって寝かせておくそうな。 品種改良に明け暮れて人間の手でいじくりまわしてダメにした。甘いみかんが売れるって、グローバルスタンダード化してどれも同じ味、おまけに流通操作の儲け主義で店に並んだ時にはすでに半分萎れてる。 こんなものが美味しいと言うのならこの国の味覚はどこか病んでいる。こんな事書くと「美味しさの原点に向かって真摯に真面目に努力している人もたくさんおられる!」と御批判を戴きそう。そうした多くの方々の努力を充分に理解し敬意を払いながら、でも、あえて暴言を続けることを許してほしい。
イタリアのみかん、マンダリンもアランチャも香り高く美味しかった。1キロ買って帰りのバスに乗れば、マンダリンの香りが車内中に広がった。何が自分達にとって本当に美味しいのか、イタリア人はそれをかたくなに守っている。フェラーリにマセラッティ、とんでもない超スピードのスポーツカーを生産し世界に輸出しているが、ローマから数キロ離れれば豊かな穀倉地帯が広がる。イタリアの友人の両親が日本にきた。東京から京都間、新幹線の車窓からみる日本の風景が、「沿線の民家と工場がづっと繋がっていて切れる所がなかった!」と驚いた。
僕はどこかいっぺんとうなこの国が軍艦島に似ているように思えてならない。石炭だったかの採掘のためだけに人が集まりにぎわった島、たくさんの家族が住まい、学校も建てられ、賑やかな子供達の声も響いた島。石炭が時代遅れになって採掘が断念された時、人は去り、翌日から時間が止まって廃虚になった。豊かさとはたくさんの価値やシステムが共存している事、一元化の波にさらされた社会は崩壊する。
グローバルな世界像とローカルな世界像をきちっとわけて考えよう。それぞれの価値観をきちっと線引きして考えてみよう。その上で相互の かかわりを模索しよう。 地方には地方の良さがあり、村興しは何も道路ばかりじゃない。今こそローカルな価値の重要性が問われている。戦後、高度経済成長の波にあおられ、置き忘れられた日本の農業をどのように立て直すか。連日のニュース番組で株と為替の変動を逐一報道する。商品経済と金融の建て直しは重要だが、日本の農業の建て直しはもっと重要な問題である。なぜならそれは金融の建て直しより遥かに時間がかかるから。
美味しさを起点とする食はまさにローカルな価値に根ざした文化。味覚とは世代を越えて伝わってきたもの。僕らはその起点を見失ってはならない。
2002/8/15
追記
僕はインターネットという顔の見えない情報媒体に疑問と恐れを感じている。誰もが、多分 平等に発信者になることができるネット。普段着感覚で気軽に手軽に瞬時に万人に向かってものが言えるネット。その手放しの気軽さが個人を傷つけることもあ。まちがった情報が世界を駆け巡ることもある。憎悪と悪意に支配されることだってある。 新聞も本も雑誌もそれは同じと言われるかもしれない。 しかしそれらには少なくともチェック機能を果たす制度がある。ネットにはそれがない。
僕はまったくインターネットというものを見ない。 今回、依頼を受けて始めてネットに流すためにこの拙文を書いた。「流すため」という言葉の感覚通り、気楽に一気に書き上げたが、依頼主への送付の段階で一瞬立ち止まってしまった。普段着感覚の気楽な文章の下に、本当は飲み屋さんで お酒でも飲みながら話すような こぼれ話しを平気で書けてしまう気軽さに僕自身驚いてしまった。言葉の奥に気づかず忍び込む嘲り、憤懣、やるせなさ。僕の拙文も誰かを傷つけているかもしれない。何度も読み替えした。数行にわたって削除もした。掲載をお断りしようかとも思った。
みかんや牛肉についても、僕はほんのわずかな行き過ぎを 捕まえて言っているに過ぎない。美味しい日本のみかんは沢山ある。
スープの味一筋、麺の歯ざわりひとすじ、苦労の果てにファンを獲得した 美味しいラーメン屋さんもたくさんある。
僕だって婦人雑誌に時折出ることだってある。
漠然とした世の中の風潮への憤り、批判する的を絞りきれていないこの手の情緒的な 漠とした雑文は、どこかで しらずに誰かを批判の為の材料にしてしまっているかもしれない。そんな懺悔の追記を付して、今日、依頼主に この拙文を送付する。誰にも平等なネット、その気軽さはネットの良さには違いない。しかし無名の大衆社会にアメーバーのように分裂を繰り返し、かってに増殖するネットが、決して自己責任を取る事のない憎悪や蔑みや妬みや中傷に支配されない事を僕は願ってやまない。
2002/9/29
樂 吉左衞門